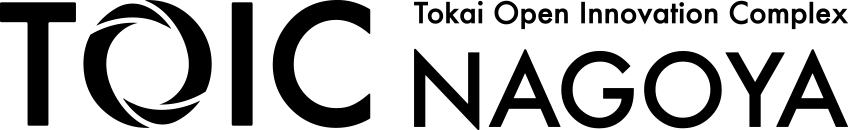【紹介していいかも!特別号・TOIC NAGOYA先生紹介リレー】#02 松本 真理子先生
#02『松本先生と一緒に”ウェルビーイング”とは何か?考えてみた!』
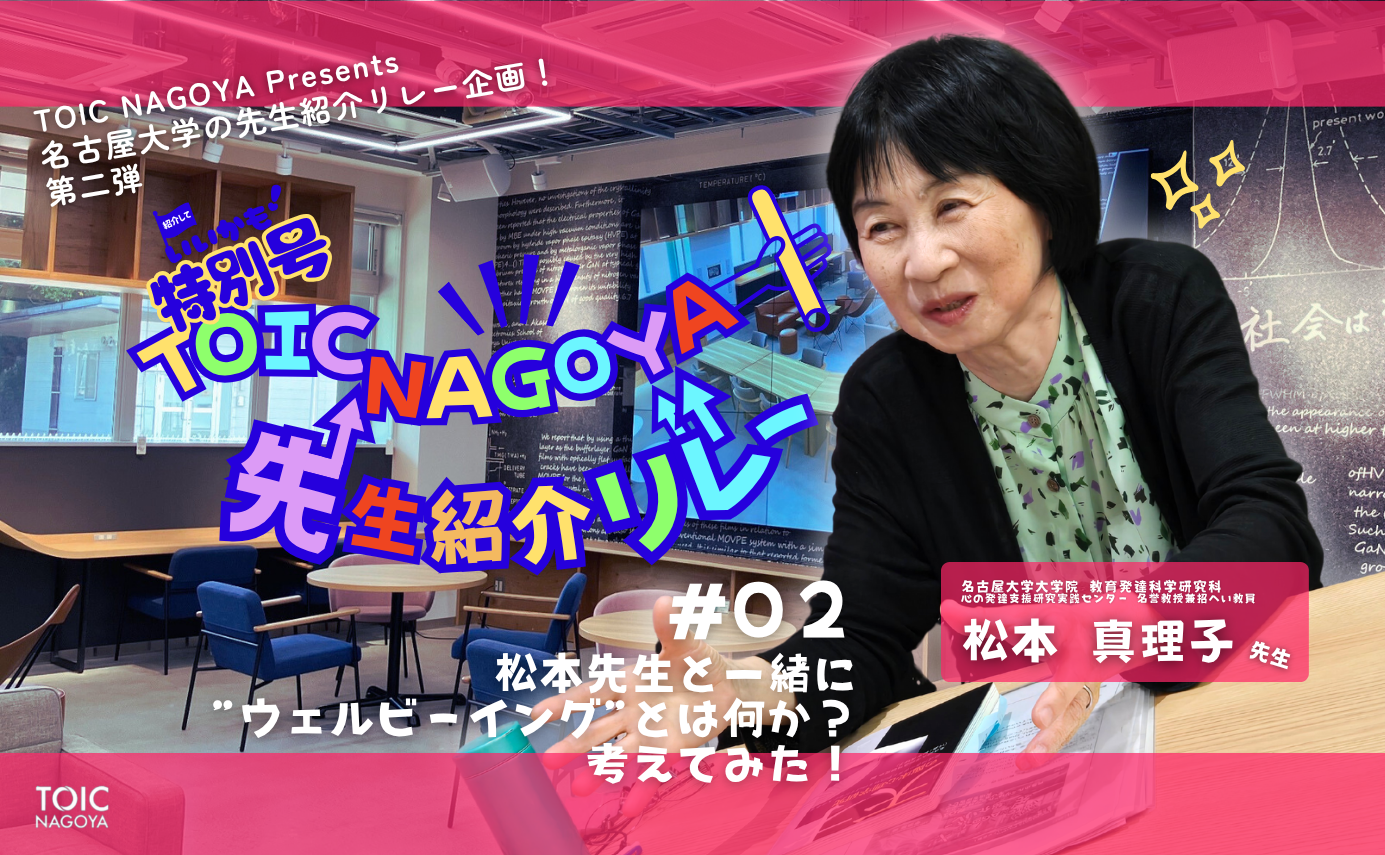
TOIC NAGOYA公式HPをご覧の皆様、こんにちは!
TOIC NAGOYA運営担当です。
TOIC NAGOYAでは、TOIC NAGOYAから見た名古屋大学内の研究者の研究内容と魅力を最大限に発信していく取り組みとして『先生同士のすてきな繋がり』にフォーカスし、先生によって先生をご紹介いただく、バトン形式のユニークな新企画、
「紹介していいかも!特別号・TOIC NAGOYA先生紹介リレー」をスタートいたしました!
第2回は、名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 心の発達支援研究実践センターより、松本真理子先生にご協力いただきました!
第1回でご紹介した宇治原先生は、松本先生の研究に協力する形で松本先生から出題される心理テストにも回答されていたのだとか・・・!?
この記事では、松本先生のこれまでや他の先生との交友関係について伺い、松本先生のご活動と魅力をあらためて発信していきます!

この企画は、名古屋大学の先生から、研究やご自身の活動のルーツについてざっくばらんにお話いただいたり、
ご交流のある先生とその先生とのエピソードをご紹介していただくことで、先生のお取組みやご自身の魅力に迫り、
先生やTOICへご興味を持ってくださった皆さんへシェアしていくプロジェクトです!
先生から先生をご紹介いただくというバトン形式リレーで、TOIC NAGOYAの各種媒体(HP、SNS)から、インタビューの様子を発信します。
TOIC NAGOYA 公式SNSのフォローもぜひお願い致します!
【TOIC NAGOYA 各種SNS】
Instagram:
https://www.instagram.com/toic_nagoya
Facebook:
https://www.facebook.com/toicnagoya/
本プロジェクトを介して先生ご自身やお取組みに興味を持たれ、ぜひ連携させてもらいたいというような、
先生と「会ってみたい」方はぜひHPの「Contact」からのお問い合わせ、もしくはTOIC NAGOYAのコミュニケーターまでご相談ください!
それでは、本編、スタートです!
インタビューご協力:
名古屋大学大学院 教育発達科学研究科
心の発達支援研究実践センター 名誉教授兼招へい教員 松本真理子先生
松本先生・ご活動:
人間関係や将来への不安、はたまた震災の時など”心の危機状況”は人生のさまざまな場面でみられることだと思います。
そのような心の危機状況に直面したとき、私たちはどのように対応できるでしょうか。
松本先生は、「臨床心理学」を通じ、子どもから高齢者まで、幅広い人のさまざまな”心の健康”と向き合い、それらをどのように評価し、どのように一人ひとりのウェルビーイング(主観的な幸福)を高めていくことができるかを探究されてきました。
特に、精神疾患の方のカウンセリングの際は、データよりも患者一人ひとりの個性を大事にすることを第一において活動されてきました。
インタビュアー:
TOIC NAGOYA 学生コミュニケーター 細居さん
——現在のテーマで研究をされることになったきっかけ
細居さん:
先生こんにちは!今日はお時間をいただいてありがとうございます。
TOIC NAGOYA、学生コミュニケーターの細居です。よろしくお願いします!
早速ですが、先生が今研究されているテーマを取り扱うことになったきっかけのようなものがあったら、ぜひそこから知りたいです。
松本先生:
臨床心理学との出会いは高校時代でした。
今の自分は、人付き合いは上手そうに見えるかもしれないけど、学生時代には人との関わりについて、苦痛に感じることがあったんですよ。
細居さん:
そうだったんですね…!先生の仰る通り、とても意外な印象を受けました。
松本先生:
高校時代、周りのクラスメイトはグループでお弁当を食べていたけれど、私はそういったグループに入れなかった。
自分は、「他の人とはなんだかズレた感覚があるなあ…」と、日常的に違和感を感じていたから、そんな自分は普通じゃないと思って…それならと自分の心を知ってみたくなったことがきっかけですかね。
細居さん:
なるほど。そんなきっかけがおありになったんですか・・・。
松本先生:
より心理学について考えるようになったのは、大学受験の進路選択の際でした。
当時の名古屋大学には、異常心理学講座(のちの臨床心理学)があったんですが、その名前を見て、「私、ここに呼ばれてる」って、直感的にピンと来るものがあったんです。
文学部心理系は、いわゆる正統派心理学分野ですが、自分自身を知っていくには、教育系の異常心理学を扱う専攻に進むべきだと考えました。
細居さん:
では、やはり、「自分自身を知りたい、分かりたい」という気持ちが、先生のスタートラインだったんですね。
——松本先生が「臨床心理学」から得た気づき
細居さん:
その後の先生は、臨床心理学を通じて、「自分自身を知ることができたな」と思えたことはありましたか?
松本先生:
臨床心理学は、基本的に対象者の心の健康回復を目指して行うものなんですが、その過程で自分のことを振り返る機会にも恵まれたような気がします。
患者さんやクライエントさんへの面接において、あるいはその後の振り返りは、「あの場面でなぜ自分はこのよう発言をしたのか」とか、「自分がクライエントの立場ならどうしただろうか」とか、自分自身の心の中を振り返る機会にもなるのです。
つまり、私たちの心理臨床と呼ばれる仕事は、患者さんやクライエントさんと関わりつつ、自身も成長させてもらう機会になるのです。
細居さん:
僕も自分への理解を深めることが大切だなと思った経験があります。
中高時代は学校の決まったスケジュールに従って生活していたから、軽度の不調に気づきにくくて、それが当たり前のようになっていたんですが、大学に入って生活リズムや人間関係を自分で管理できるようになると、体調や気分が改善されたことがありました。
そこで、体調不良が、後から精神状態に裏付けされていた行動だと知って…。
先に知っていれば予防ができるんじゃないかと思ったことがあります。
松本先生:
臨床心理学を通して感じたのは、自分のことを知ることの重要さかな…。
自分を含めて、すべての人にはもちろん欠点もあるんですが、それを受け入れたうえで、どのような能力があるのか、得意な側面があるのかを知ることは、有能感に繋がる大切なことです。
私の研究テーマの1つに「子どもを取り巻く環境と心の健康支援に関する研究」があるんですが、これはすべての研究テーマのはじまりなんです。
心の具合の悪い子どもたちはとてもたくさんいて、ある悩みをかかえて不登校になった子どもが、臨床心理士(公認心理師)の支援で元気になる。ヤレヤレ、と思っても同じような子どもが次々と受診や相談にくるのです・・・これの繰り返し。
こういう子どもたちを少なくするためには、さっき細居さんが使った言葉だけれど、『予防』が重要なのではないかと考えはじめました。
そうしていくうちに、子どもの心の健康に結びつくのは『環境』…すなわち、学校と家族という2大環境がともかく基本であると気づきました。
心の健康はすべての基本ですからね。

会話が盛り上がっていく二人。
細居さん:
どんな研究にも言えることだとは思いますが、松本先生の研究されている分野においても、きっと苦しいこと、難しいことが絶えないんじゃないかと思います。
敢えてそういった点についてもお聞きしてみたいのですが、良いでしょうか。
松本先生:
カウンセリングや患者さんのケアに関することでいえば、面接がこちらの予想どおりにいかず、被験者の方が気分を害されてしまったりとか・・・そんな風に、被験者の方との関わり方がうまくいかないときはすごく苦労しました。
しっかりした信頼関係ができると相手の感情が引き出されてきて、それ自体は必要な過程なんですが、一方で患者さんと真剣に、時にはバトルしなければならない(ケンカするわけではないですよ)ときが苦しいです。
客観的な評価も重要で、それも時に苦しかったり、患者さんに怒りを覚えてしまったとき、そんな自分を顧みていく過程が苦しいですね。
細居さん:
人間同士の会話だからこそ、距離感が詰まっていくのはいいことでもあり、難しいことも出てきますよね・・・。
松本先生:
そうですね。研究の面で言えば、データをとることもなかなか厳しいところですね。
生身の人間を相手に、数値的に測定するという作業は、時間がかかりますし、難しいですね。
細居さん:
では、松本先生はどんな瞬間に「嬉しい」と感じますか。
松本先生:
患者さんへのケアで言えば、もちろん自分がかかわってきた(支援してきた)子どもたち、青年、大人たちがカウンセリングを必要としなくなった時が何よりも嬉しいです。
研究で言えば、色々な苦しいことを乗り越えて、結果が出たり、新しい発見があると嬉しいですし…これは研究をしている皆さんにも言えることだと思います。細居さんもそうでしょ?
細居さん:
はい。僕も研究をしているので、辛い経験や悩みを乗り越えて結果が出ると嬉しいです。
「認識がひろがる」経験というか・・・
松本先生:
そうそう。私は学生さんに、そういう体験をたくさんしてほしいと思うんです。
細居さん:
心の健康という言葉が出ましたが、そもそも松本先生は「幸せ」をどう定義されていますか。
松本先生:
私が定義する幸福とは、「本人が幸せと思っているかどうか」という主観的幸福感が何よりも重要であると思っています。
SCT(私が幸せなときは~)という指標でテキスト分析をするんですが、それらを解析していくと、人の幸せに必要な要素は大きく分けて「達成感」、それから先ほど少し話題にあげた「有能感」、そして「生命感(人と結びつくこと)」の3つに分けることができるんです。
——松本先生の大切にしている考え方
細居さん:
松本先生が研究をされていくなかで、大切にされている考え方であったり、
過去、誰かから言われて大切にしている言葉だったり・・・そういったモットーはあったりしますか?
松本先生:
研究のこだわりとしては、大学時代の恩師が、患者さんへの現象学的接近を重視される先生だったので、その先生に倣い、客観的データだけをみるのではなくて、目の前に存在する患者、クライエントの個別性を何よりも大切にするカウンセリングを心がけています。
例えば、発達障害の診断をされている方々に対しても、発達障害として一律に接するのではなくて、個々人に違ったアプローチをしています。
それぞれの患者さんの特徴に寄り添ったうえで問題を解決することを大事にしています。
細居さん:
僕の研究している自然科学の分野においては、データやエビデンスを重視して、極力、主観性を除いて考えますが、松本先生の場合は先生ご自身の経験やインスピレーションも大切にされているんですね。
松本先生:
もちろん、臨床心理学においても、色々な数値的な指標を用いて人の性質を評価することはあります。けれど、そのように人を数値的な面だけで理解しようとするのではなくて、当たり前のことなのですが対象を一個の人間として見ることを同時に大切にしています。
どちらも大切な視点ですね。
——松本先生がこれから挑戦してみたいこと
細居さん:
松本先生が活動を通じて大切にされている考え方について知ることができて嬉しいです。
これからの展望や、注力していきたいことについても教えてください!
松本先生:
たくさんありますね…。今はシニア層にも関心があって、対人関係とウェルビーイングを軸に高齢者を対象とした研究をしてみたいと考えています。
細居さん:
そうなんですね。そこだけを聞くと、先生がこれまで対象にされてきた年齢層や、子供を相手にするより難しそうな印象を受けます。
松本先生:
どうしてそう思ったんですか?
細居さん:
僕個人としては、コミュニケーションがうまくいかなくなった時、子供になら激昂されてもいいんですが、年上に激昂されるのは怖くて。それに気を遣うので…
松本先生:
実は、高齢になって人生の終わりを意識しながら生きることと、ウェルビーイングには深い結びつきがあるんです。例えば、介護施設で職員さんに「この人は怒りっぽいな」「困った人だな」と思われている人がいたとしても、彼らにも想像する力やクリエイティビティがあると思っています。ただ、それがウェルビーイングと結びつく形で発揮されていない。
ロールシャッハ・テスト※の反応において、クリエイティビティを示唆する反応があるんですが、それは高齢者にも出現する。ただ現実的な形で発揮されないと、「だからこの人は頑固おやじなんだ」などと、ネガティブな結論になる傾向があります。
高齢の方を対象とした対人関係に関する臨床心理学研究はまだ少ない現状にあります。
そんな中で、高齢の方に対して周りの人間がどうサポートしたら、そうしたクリエイティビティが発揮されたり、対人関係からウェルビーイングが実現されるかに関心があります。
細居さん:
なるほど、勉強になります。
一方で、松本先生といえばこれまで学生に対しても親身に支援をされてきたので、そういった方面での今後はどのように考えていらっしゃいますか。
松本先生:
エネルギッシュな高齢者…例えば、定年後の先生、天才と評価された研究者、そういった方々と学生をマッチングして、サポートしてもらったら面白いんじゃないかと思ってるんです。
一般の方より、天才と称される研究者のほうが、ウェルビーイングが高いんです。
全学学生相談センターのセンター長になり、全学の学生や教員とかかわる機会が増えたのですが、理系の先生方のおられる教授会を回ると、変人と言われそうな天才的研究者が、学内には相当数存在して、変人と言われようが、ウェルビーイングな人生を楽しんでいるんです。
一方で悩んでいる学生たちがいるのは、なぜか、何が違うのか、ということから臨床心理学教員で名古屋大学創造性研究会を発足させて、理系研究者や院生を対象に研究してきました。
(協力者の一人が前回の記事で紹介した宇治原徹先生です!研究の詳細は「天才の臨床心理学研究」(遠見書房、2024)をご覧ください。)
そして、研究者にはとても個性的で、その個性は時に現実枠をはずれているような方が多いことに気づきました。
けれど、みんなが自分らしく幸せに生きている。
それと同時に、発達障害傾向のスクリーニング調査を全学で実施したところ、発達障害圏の可能性のある学生がとても多かった。さらには大学に来られない学生の多いことにも気づきました。こういうことやりたいな、こんな発明をしたいな、という研究を突き詰めて天才と評価される大人(教員)がいて、これってすごく幸せな生き方なのに、一方で潰れそうな学生もいるんです。
だから、幸せに生きている超変人な天才の先生がこういうTOICのようなところに来てくれて、サポートが必要な学生さんが気軽に来れるような、『大人版子供会』みたいな催しができたら素敵じゃありませんか。
細居さん:
はい、とても素敵だと思います!
発達障害があったり、学校へ通うことが難しい、色々な面で支援が必要な学生さんたちに対して、どういう方向に向かってほしい、成長してほしいというようなお考えはあったりしますか。
松本先生:
どういう方向に、というのは、自分で決めることだと思うけれど、まずは自分の持っている力を知る場が必要ですね。
なので、TOICをそんな使い方ができたら良いななんて思っていますよ。
※
スイスの精神科医ヘルマン・ロールシャッハによって開発された、左右対称のインクの染みを見て、それが何に見えるかを答えることで、人の性格や深層心理を分析する心理検査
——松本先生は、今、幸せですか?
細居さん:
ズバリ、松本先生の今の幸福度は10段階中いくつですか?
松本先生:
え~!難しいですね~…でも8から9くらいかな?
細居さん:
結構高いですね!
じゃあ、今と、昔とを比較したらどっちが幸せですか?
松本先生:
昔は、子育てと仕事を両立させなければいけなかったりとか、肉体的に辛いこともあったけれど、それはそれで充実していましたね。
細居さん:
今の先生と、一番忙しかった頃の先生と、どちらがウェルビーイングに近いか比較することはできないということでしょうか?
松本先生:
細居さんは私の答えを聞いて、どう思われましたか?
細居さん:
まるっきり自由で制限がない時間を過ごしていても、やがてその状況に慣れて退屈になるんじゃないかと思うんです。例えば、仕事や、僕で言えば研究室だとか、そういう「やらなければいけないこと」という制限があるから、自由な好きな時間が余計楽しく感じるんじゃないかなって。
嫌なことと、楽しいこと、ウェルビーイングって、実は切り離せないんじゃないかな・・・。
松本先生:
面白いですね~…!
なんだか私がカウンセリングを受けてるみたいで、新鮮な気持ちになりますよ。

「ウェルビーイングとは何か」、松本先生とのお話のなかで自分なりの答えを見つけた細居さん。
————松本先生から、次の先生のご紹介
細居さん:
ここまでのお話、ありがとうございました!
僕たちは、この企画を通じて、先生方ご自身についてや、お取組みを紹介するうえで、先生同士のご交流についても発信することで、お人柄や魅力をより伝えたいと考えています!
今回インタビューさせていただいた松本先生から、また他の先生のご紹介をいただきたいのですが…どなたをご紹介いただけそうでしょうか?
松本先生:
どんな先生がいいでしょうね~…あ、細居さんも授業を受けたことがあるなら、
渡邉雅子 先生
(名古屋大学大学院 大学院教育発達科学研究科 教育科学専攻 学校情報環境学 教授)
にご協力いただくというのはどうでしょう?
細居さん:
ぜひお話を伺ってみたいです。
渡邉先生の授業は興味深かったので、今度は是非インタビュアーとして直接コミュニケーションをとってみたいです!
松本先生:
渡邉先生は私と同じくらいの時期に名古屋大学にいらして、同じ棟で研究されていたご縁もあるんです。
非常に知的で、『THE研究者』というイメージ…!無駄が一切ないですし、出版された本も、先生のイメージそのもの!という印象を受けましたね。かっこいい方だなあと思っています。
細居さん:
ありがとうございます!
では、最後に渡邉先生に向けて、メッセージをお願いいたします!
松本先生:
本をきっかけに渡邊先生に興味を持たれた方がより増えたことを嬉しく感じています。
TOICでの活動や、TOICを利用することでそういった方々との素敵な繋がりを産んで、益々のご活躍のきっかけにしていただけたらと思っています!
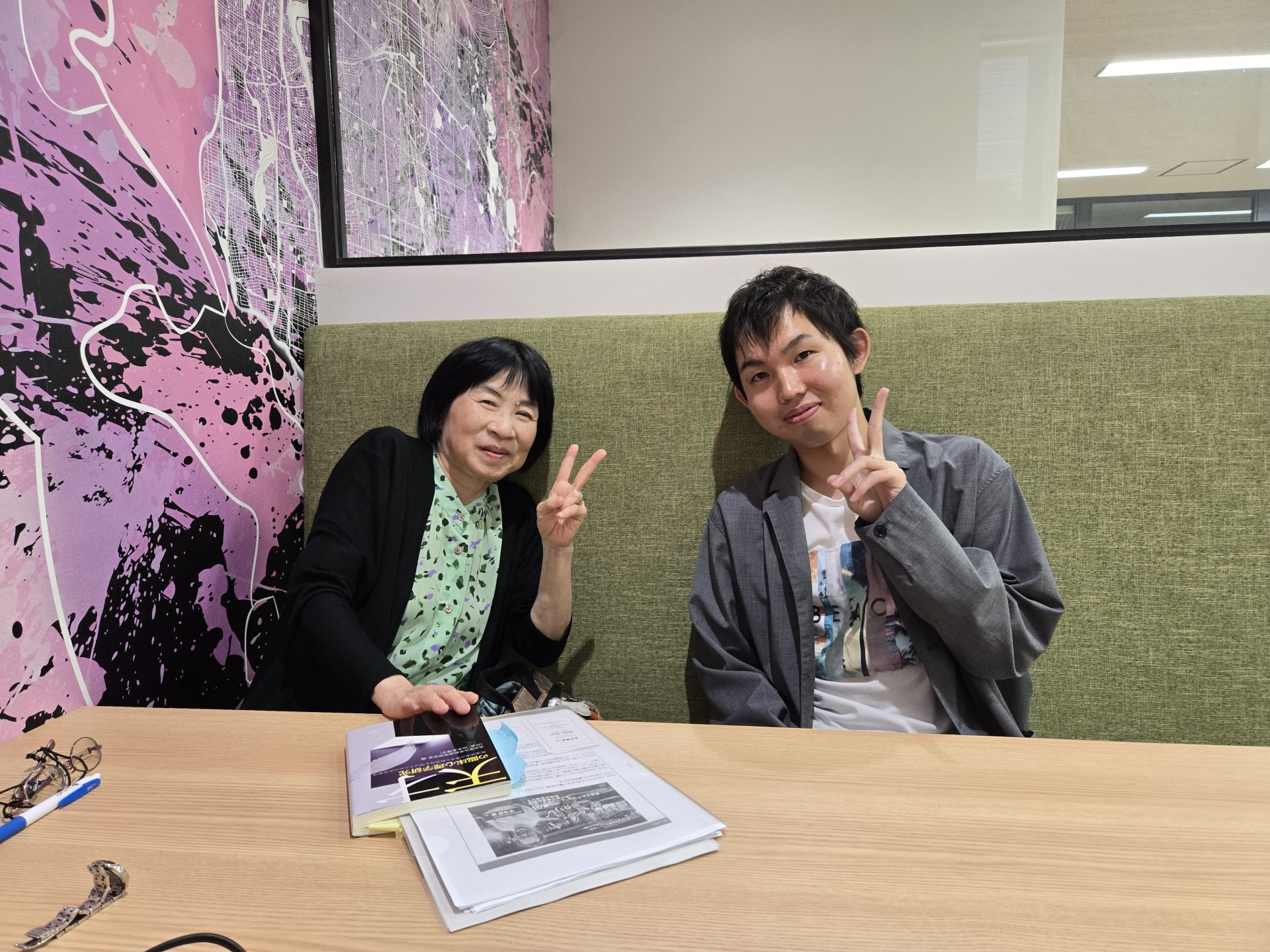
最後はお揃いのポーズでパシャリ!松本先生、本当にありがとうございました!
——松本先生にお話を伺ってみて
僕は普段、生命理学科で生物の研究をしていることもあり、「人の心は、どうやって科学的な対象として捉えるんだろう…」と不思議に思っていました。松本先生とお話をしていく中で、人の心というものを科学として客観的に調査するのと同時に、人としての主観的な認識を大切にされているのだと感じ、僕にとってはすごく新鮮なお話でした。
インタビュー後、性格検査の代表的な方法の一つであるロールシャッハ・テストを実際に体験したのですが、ほとんど経験したことのないようなタイプのテストで、とても面白かったです。
相手に対する敬意は持ちながらも、思ったことはしっかりと伝えてくださる先生ですので、心理的なことで不安があったり、自分について興味があったりする人は、ぜひ松本先生に会って話してみてほしいと思います!
(インタビュアー・細居さん)
——おわりに
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
「紹介していいかも!特別号・TOIC NAGOYA先生紹介リレー」第2回はいかがでしたでしょうか。
今後も名古屋大学の先生から、研究やご自身の活動のルーツについてや先生同士のご交流について伺い、発信していきます。
次回ご紹介する先生は、
名古屋大学大学院 大学院教育発達科学研究科 教育科学専攻 学校情報環境学 教授
渡邉雅子 先生です。
お楽しみに!