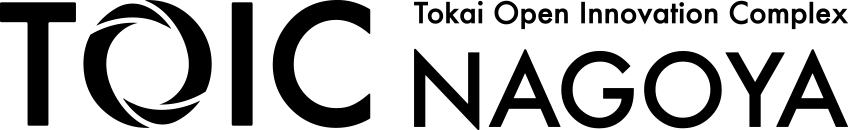【紹介していいかも!特別号・TOIC NAGOYA先生紹介リレー】#01 宇治原 徹先生
#01『先生のルーツは”ルーツ好き?!”学びあう未来の大学実現を目指して』

TOIC NAGOYA公式HPをご覧の皆様、こんにちは!
TOIC NAGOYA運営担当です。
TOIC NAGOYAでは、この度、TOIC NAGOYAから見た名古屋大学内の研究者の研究内容と魅力を最大限に発信していく取り組みとして
『先生同士のすてきな繋がり』にフォーカスし、インタビューした先生から、次回インタビューする先生をご紹介いただくリレー形式のユニークな新企画・「紹介していいかも!特別号・TOIC NAGOYA先生紹介リレー」をスタートします!
記念すべき第1回は、名古屋大学 未来材料・システム研究所未来エ レクロトニクス集積研究センターより、
宇治原徹先生にご協力いただきました!
TOIC NAGOYAへご入居されている株式会社U‐MAP、アイクリスタル株式会社にて取締役をされているということもあり、
日頃からTOIC NAGOYAにて社員のみなさんや利用者さん、そしてスタッフとも交流をしてくださっている宇治原先生。
この記事では、宇治原先生のこれまでや他の先生との交友関係について伺い、
宇治原先生のご活動と魅力をあらためて発信していきます!

この企画は、名古屋大学の先生から、研究やご自身の活動のルーツについてざっくばらんにお話いただいたり、
ご交流のある先生とその先生とのエピソードをご紹介していただくことで、先生のお取組みやご自身の魅力に迫り、
先生やTOICへご興味を持ってくださった皆さんへシェアしていくプロジェクトです!
先生から先生をご紹介いただくというバトン形式リレーで、TOIC NAGOYAの各種媒体(HP、SNS)から、インタビューの様子を発信します。
TOIC NAGOYA 公式SNSのフォローもぜひお願い致します!
【TOIC NAGOYA 各種SNS】
Instagram:
https://www.instagram.com/toic_nagoya
Facebook:
https://www.facebook.com/toicnagoya/
本プロジェクトを介して先生ご自身やお取組みに興味を持たれ、ぜひ連携させてもらいたいというような、
先生と「会ってみたい」方はぜひHPの「Contact」からのお問い合わせ、もしくはTOIC NAGOYAのコミュニケーターまでご相談ください!
それでは、本編、スタートです!
インタビューご協力:
名古屋大学 未来材料・システム研究所
未来エレクトロニクス集積研究センター 宇治原徹先生
宇治原先生・ご活動:
現代社会はAI、IoT(Internet of Things)、ロボット等先端技術が実装されていき、ますますの発展が予測されます。
そうした未来において、切っても切り離せない”環境問題”。
宇治原先生は、持続可能な未来の社会の実現に向け、【電気】と【熱】の観点から研究開発をされています。
様々な研究テーマの中でも、熱問題の課題解決に向けては、極めて高い放熱性を持つ絶縁体・AlN(窒化アルミニウム)を用い、より電気の変換効率の高いパワー半導体の開発のために、現行のシリコンの約10倍の特性が期待されるSiC(シリコンカーバイド)に注目し、既存の材料を改良するなど、我々の生活を豊かにする様々な製品の材料に対して、新たな可能性を拡げる取組みをされています。
インタビュアー:
TOIC NAGOYA 学生コミュニケーター 細居さん
——現在のテーマで研究をされることになったきっかけ
細居さん:
先生こんにちは!今日はお時間をいただいてありがとうございます。
TOIC NAGOYA、学生コミュニケーターの細居です。よろしくお願いします!
早速ですが、先生が今研究されているテーマを取り扱うことになったきっかけのようなものがあったら、ぜひそこから知りたいです。
宇治原先生:
高校生の時から、世の中を変えたいという気持ちがあったんだけど、
物事のルーツを探ることに関心があって、世の中のことは人の心も含めてすべて理屈で説明できるはずだ!と思っていたんだ。
ペンは剣よりも強し!みたいな感じで、新聞記者になるのもいいなあと思ったこともあったよ(笑)
細居さん:
もともと文系の進路にご興味があったんですね!意外でした…
でも、その熱意がありつつも、今はまったく違うテーマを研究されていますよね。
宇治原先生:
当時、学生が無償で留学できる制度があったから、その制度を利用して海外へ行くことも考えたけれど、
自動的に1年間留年になってしまうのと、面接でも縁がなくて文系の進路はとらなかったんだ。
それから色んなことを考えたけど、世の中のルーツをすべて説明ができる、かつ世の中を変えられるのは『材料』なんじゃないかと思いはじめて。
先生からも、「世界を変えるなら工学、ルーツを考えることが好きなら材料。 金属工学だ」って
言葉をかけられたし、もともとマテリアル系に興味もあったから、改めて京都大学の理学部を目指すことにしたんだ。
でも、成績の面ではずっとE判定だったから、先生からは京都大学に行くのは無理だって言われたけど、
僕は京都大学しか頭になかったから、高校3年生の時に『この1年間、とにかく意地でもやってやる!』って決めて、
もうがむしゃらに勉強したよ!
細居さん:
目標に向かって諦めずに、粘り強く取り組まれたんですね・・・。
宇治原先生は、どうしてそんなにも京都大学に対して魅力を感じてらしたんですか?
宇治原先生:
僕にとっては、自由がないっていう状況が一番嫌なんだけど、京大生には『自由へのお墨付き』があると思っていて。
京都大学は、勉強をただ教わりに行くのではなくて、面白い人が集まっているし、そこでの出会いを大切していく、
そういう、自ら学びに行くっていう風土があったから、 京都大学は自由だと思ったんだよね。
僕が大学受験をした当時は一浪もあたりまえで、ある意味そういう、「チャレンジしても良い」って言ってもらえる環境があったからこそ
たとえ他人に無理だと言われるようなことに対しても、最初からチャレンジしないなんてことは考えられなくて、授業もそっちのけでひたすら勉強した。
結果的に成績はE判定からD、受験直前にCまで伸ばせて、
大嫌いだった古典も2週間集中して克服したんだけど、そうして諦めずに粘り強く勉強をして、京都大学に行けたことは、
人生の中でも大きなポイントだったね。
何かをやるって決めたらがむしゃらに、最後の1秒まで粘るというのは今も変わらない。
最後の1秒まで粘れば成功確率があがるんじゃないか?って信じてるよ。
——研究に没頭する日々のなかで
細居さん:
最後まで諦めずに目標に向き合って、達成できた経験が、人生のターニングポイントになって・・・
今でも物事に対して最後まで粘り強く打ち込むということを、変わらず大切にされているんですね。
その後の先生は、進学や研究の中でどんなことに熱中されたり、どんな考えがモチベーションになっていったんでしょうか。
宇治原先生:
今度は材料のことを考えていくうちに、ゴミが無くなればいいなと思うようになった!
環境問題にも関心があったし、全ての材料が劣化することなく使い続けられたら、ゴミは出ないよね。
始めは劣化しない、壊れないものを作ろうとしていたけど、そのうちに土に還る材料を作ることを目指していった。
細居さん:
環境問題への関心かあ・・・。金属材料にも、色々な種類や特徴がありますよね。
宇治原先生:
そう!鉄にも色々あるんだよ。
日本刀なら固くなければいけないし、車はある程度柔軟性が必要。
金属も顕微鏡で見ると、細かい模様があってね・・・その模様がとってもきれいで!
シマウマの柄やお星さまみたいなものとかがあってさ・・・
そういう、規則的な模様の美しさみたいなものに魅了されて、
修士、博士課程の間は、パターン形成に関する理論の研究をして論文を書いたよ。
あの時は実用性より、パターン形成そのものに熱中してたよ(笑)

笑顔でお話を聞かせてくださる宇治原先生。
細居さん:
きれいな模様を観察して、その中から規則性を探っていく、ということですか・・・楽しそうです!(笑)
でも、そのパターン形成に熱中されていたタイミング的には、僕だったらどんな進路をとるかとか、成果をあげなくちゃとか、
焦りが出てきちゃうんじゃないかなと思いました・・・
宇治原先生:
そうだよね。
僕がラッキーだったのは、僕に付き合ってくれる先生がいたこと!
でも研究の方は、当然うまくいかないこともあって、毎日ずっと同じ計算式のあるところで躓いたことがあったんだよね。
挫折しかけて、先生に相談して違うテーマに没頭したこともあったけど、結局元のテーマに戻ってきちゃうんだよね(笑)
それで、相変わらず解けない計算式に向き合うんだけど・・・
博士課程2年のある冬の日に、直感でピキーン!って何かが降りてくるような感じがしてさ、
その感覚のまま躓いてた式に向き合ってみたら、答えが出ちゃった!
細居さん:
え!?
僕もその、挫折みたいな気持ちがわかりますけど、そんなことってありますか!?(笑)
諦めなくて本当によかったですよね・・・!
宇治原先生:
そうそう(笑)
挫折を乗り越えて、研究テーマの面白さに気づけたんだけど、
博士課程4年の時に、論文を書くうえで文章そのものの書き方なんかも見つめなおして、
その後は東北大学の金属材料研究所で結晶成長に関する研究をしていたよ。
企業出身で応用研究寄りの考えをされる先生と、基礎研究をしてきた自分とで、
コミュニケーションに難しさを感じたこともあったけど、相手の話を理解するためには・・・っていうのを考え始めて、
よくよく相手の話を聞いたら、自分の考えと親和性があったんだ。
そこで応用研究と基礎研究は両立できるっていう気づきがあった。
それからまた結晶成長の研究が進んで、そのうち、SiC(シリコンカーバイド)の結晶成長の世界に踏み入れたことを機に
名古屋大学へ来たんだ。
——起業について
細居さん:
今までのご研究について教えていただき、ありがとうございます!
宇治原先生といえば、たくさんベンチャーを起こされていますけど、起業をしようと思ったタイミングはいつだったんでしょうか?
宇治原先生:
今まで、結晶の高品質化を目指してやってきてたんだけど、周囲の企業が離脱しはじめて、
せっかくの技術の実装にチャレンジする会社がなくなってしまったんだよね。
品質だけでなく、結晶を大きくすることも必要で、その部分を担ってくれる会社がいなくなってしまったことを機に、結晶を大きくするための技術に取り組みはじめた。
誰も研究していないテーマでナンバーワンになりたいと思ったから。
細居さん:
なるほど・・・
環境の変化と、熱意とが合致して、みたいな感じですね。
でも宇治原先生なら、その技術を突き詰めていくうちに、また何か新たなことに取り組まれるんじゃないか・・・!と思ってます(笑)
宇治原先生:
結晶を大きくする技術に取り組んでいくうちに、その技術のために要する時間に注目して、
AIの重要性に気づいてAIは研究テーマの1つになったよ。
起業の話に戻ると、とある会社の社長さんにとんでもない背中の押され方をして(笑)
「研究を実用化するにはこの手があるよ、…社会実装するにはスタートアップにするのが早いよ!」
なんて言われたり・・・僕は以前、 博士課程教育リーディングプログラムにも関わっていたんだけど、
そこでもどんどん周囲の先生が起業していくんだよ!(笑)
そういう影響もあって、やってみるか!って。
細居さん:
ありがとうございます!
協力関係にあった企業が減るというタイミングだったり、起業に意欲的な先生方がいたり、
そんな環境も相まって、起業に至ったということですね・・・!
宇治原先生:
そのうちに「未来マトリクス」を立ち上げた時、学生と、アイデアのない地元中小企業をくっつけようマッチングしてみたらどうかなっていう考えで活動していたんだけど、
その中でスタートアップ界隈の方と出会って、そういった方々から刺激を受けて、「みんなの知恵を集めるってすごい」と思った!
——宇治原先生が大切にしている、『学びあい』という考え方
細居さん:
ここまで、今の先生を築いてきた、ルーツの部分をお話いただいたのですが、
その中でもこれからも、ずっと大切にしているモットーや考え方の部分をお聞きしてもいいですか?
宇治原先生:
僕はずっと、教える、教えられるっていう関係が苦手でね。
学生の頃、自分がナンバーワンになりたいんだったら、「まずは目の前にいる先生を超えなきゃダメじゃん!」
って思ったりした(笑) 僕はずっと、知りたいし、学びたい。
細居さん:
先生から生徒に対してだけとか、一方通行じゃなくて、リスペクトみたいな感じでしょうか。
宇治原先生:
そう、先生から学ばせてもらうんじゃなく、学びあい。
僕が知らないことは学生から教えてもらうこともあるし、僕しか知らないことと、
スタートアップのみんなから学べることがくっつくから素晴らしいものが生まれて、それってすごいよね。
僕は学生時代、自宅の近くの飲食店でアルバイトをしていたんだけど、そこのマスターが閉店後にお店でよく仲間を集めて宴会をしていてね。僕は住まいが近いから毎回呼ばれて、二つ返事でそこに行くと、そこにはマスターの知り合いの色んな人がいてさ。
お坊さんだったり、領事館に知り合いのいる人だったり・・・
京都っていう土地柄と、マスターの交友関係もあって、本当にいろんな人がいたんだ。
やんちゃな学生だった僕のことを、全然業種も背景も違う色んな人が可愛がってくれた。
今思うとあれはサロンだったなって思うよ!(笑)

学生時代のエピソードで盛り上がる宇治原先生と細居さん。
細居さん:
それは楽しそうですね!
そのご経験も、今の先生のルーツだったり、学びあいの話に通じてくるんですね!
宇治原先生:
そう!だからTOICももっとおもしろいことを増やそうよ!
自分が知らないことを知っている人を呼ぶ、そういう風に、TOICに来た人1人1人にとって
まったく違う人と触れ合える場になっていったらいいんじゃないかな。
学びあい、知っていることを享受しあう仲間づくりができたらいいよね。
一方で、「サイエンス」って、言葉から難しそうなイメージが定着して、みんなで協力できるっていう状況を作りづらい。
サイエンス自体が、いろんな人に対してオープンではいないんだよね・・・
細居さん:
そうですよね、実際に必要な知識が多いですし、正確性を避けられないから、芸術のように、
感性でこれは「よいもの」、と判断したり、人によって感じ方が違ってもよい、という風にはできない・・・
知識をインプットする量も1つハードルな気がしています。
宇治原先生:
そう。
なんでこうもみんなで協力できない、閉鎖的な環境なのかなって思う。
サイエンス自体がオープンになっていったら、もっといろんな世界が拓けていくよ!
細居さん:
もっと身近に、それこそ流行ったりしたら・・・
宇治原先生のよくおっしゃる、『ポップサイエンス』ですね!(笑)
宇治原先生:
サイエンスやってるやつってイケてるっていう時代を作りたいな〜!
だから最近は民衆化、大衆化、そういうムーブメントの起こりは どこから来るんだろう?っていうことに関心があるんだ。
音楽も、かつてはクラシックがメジャーで、 それが時代とともにどんどんポップが台頭していったみたいに、
その道をサイエンスが辿るなら・・・って考えてるよ。
細居さん:
正確性とか、情報のインプットとか・・・そういう部分を機械やAIにもっと任せられたらいいですよね。
宇治原先生:
サイエンスにおいての情報のインプットとか、
機密性みたいなところを機械に任せたとしたら、残る要素って「イマジネーション」で。
このイマジネーションって、人が自分しか知らないことを学びあっていくことで、前進していくと思うんだ。
だから、大学は学びあいを促進する、チャレンジができる場である必要があると思ってる。
ポップサイエンスっていうのも、そういう大学の在り方のうちの1つ!
——宇治原先生のこれから。「未来の大学」について
細居さん:
ありがとうございます!
大学の在り方、学びの在り方の部分に、今のDセンター※等でのご活動にも影響があるのかなと思うのですが、
これからの展望や、注力していきたいことについても教えてください!
宇治原先生:
大学は専門性を学ぶ場だけど、そこに『現場』と『ビジネス』 を加えることで、
専門を生かして、実践的な、あるビジョンをもって活動する人間を育成したいと思ってる。
細居さん:
なるほど・・・ありがとうございます。
今の学び方に、実践的な要素が加わるということですね・・・なんだか『未来の大学』という印象です。
宇治原先生:
僕は、何らかの形で人に影響を与えることは、すべてイノベーションだと思っている。
これからは、AI等を駆使してあらゆるものごとを『情報化』して、
その情報に新しい意味を掛け合わせたら、そこでイノベーションが生まれるでしょ?
これってわかりやすく例えると、既存のカードに違うカードを掛け合わせて新しい効果が生まれる・・・
カードゲームと一緒!(笑)
細居さん:
未来の話だけど、すごく身近に感じてきました!(笑)
情報っていうカードが揃っているのが大学ですね。
宇治原先生:
そうそう!カードが揃っているのが大学で、情報をインプットする部分をAIに任せたら、
大学は自分のアイデア、イマジネーションを発信する場になるよね。
そうなると、新しいカードを生み出せる大学が魅力的で、価値ある大学になっていく。
大学はアイデアのトレーサビリティを担保して・・・
そうしていくともう、未来の大学は強固なプラットフォーマーになる!
そういう、未来の大学像の最たるものをDセンター※で創っていきたい。
それで、そこにいる人たちに「あなたは今、大学で何をしているの?」って聞いてみたい!

未来の大学の在り方について、自身の考えをお話しくださる宇治原先生。
※名古屋大学ディープテック・シリアルイノベーションセンター
学士課程から博士後期課程まで階層的に、大規模かつ学際的にアントレプレナーシップ教育を行う機関。
——宇治原先生から、次の先生のご紹介
細居さん:
ここまでのお話、ありがとうございました!
僕たちは、この企画を通じて、先生方ご自身についてや、お取組みを紹介するうえで、
先生同士のご交流についても発信することで、お人柄や魅力をより伝えたいと考えています!
今回インタビューさせていただいた宇治原先生から、また他の先生のご紹介をいただきたいのですが・・・
どなたをご紹介いただけそうでしょうか?
宇治原先生:
う~ん、どうしようかな・・・面白い先生はいっぱいいるよ?誰がいい?!(笑)
・・・あ、あえて僕のやってることとまったく違う、文系の先生はどうだろう?
細居さん:
文系の先生は、僕が理系なこともあってなかなか出会えていないのでとっても嬉しいです!
TOICや、こういった企画にも興味を持って下さりそうな先生はいらっしゃいそうでしょうか?
宇治原先生:
わかった!じゃあね、松本真理子 先生に繋いであげるね。
(名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 心の発達支援研究実践センター 名誉教授兼招へい教員)
こういうことに快く協力してくれるから。
細居さん:
ありがとうございます!
松本真理子先生のお取組みについて、しっかり調べてみます。
ちなみに、宇治原先生とのご関係性や、出会いはどんな感じだったんですか?
宇治原先生:
出会いは2018年頃になるかな?
当時はCIRFE(シルフェ/未来エレクトロニクス集積研究センター)の学生相談室が活用されていなかったから、
カウンセラーに来てもらおうという話になったんだよね。
それで、僕から「学生に来てもらうことに対するハードルを下げるために、常駐してくれる人が欲しい」って相談をした先生がいたんだけど、その先生からの紹介で松本先生と知り合ったんだ。
心理学を専門とする松本先生なら、マイナスな状態の心をケアして0にすることができるし、
そんなことができるなら、ケアを必要とする人だけでなく、誰に対してもプラスへ向くような支援をしてくれるんじゃないか?と思ったんだよ。
細居さん:
そうだったんですね!
そういった切り口からも学生への支援を強化しようとされたんですね。
宇治原先生:
松本先生は、「研究者のクリエイティビティがどう生まれているのか、心理学的に分析したい!」といって、
僕も研究に協力する形で2年くらい、松本先生から出題されるいろんな心理テストに答えたりしたよ(笑)
細居さん:
宇治原先生が研究対象になっていたんですね!(笑)
そんなおもしろい関係性だったなんて・・・じゃあ、今はお会いした時どんなお話をされるんですか?
宇治原先生:
たくさんのお菓子を用意して、たわいない話するよ(笑)
最近なにがあったんですかとか、別にそんな感じ!
でもね、松本先生は研究者を心理学で分析して、それを教育に落とし込むことをされているんだけど、
「教育から天才を作ったるぞ!」っていう考えがあるね。
優しい雰囲気の先生なんだけど、自分の取り組みでこういう人材を生み出す!っていうことに対するパッションを感じる。
細居さん:
なるほど・・・!
宇治原先生との共通点というか、似ているかな?と思うようなところをお持ちなのかなと思いました!
宇治原先生:
そうだね。
今の教育の在り方だけが完全な正解ではないっていうのは、僕もそう思っているかな。
細居さん:
ありがとうございます。
では、最後に松本先生に向けて、これから一緒にこれからこんなことをしたい!ですとか、
メッセージがあれば教えてください!
宇治原先生:
分野は違えど、人材育成の新しい方法論にヒントを与えたい、そういう考え方の方向性は一緒だと思うので
松本先生にも一緒に新しい大学や学びの在り方を一緒に考えてもらいたいです!

最後はお揃いのポーズでパシャリ。
宇治原先生、本当にありがとうございました!
——宇治原先生にお話を伺ってみて
何度かお会いしたことがある宇治原先生でしたが、会うたびに新しいお話をしてくださる方で、
今回も話をお聞きしていて非常に面白かったです。
特に今回は先生インタビューということで、これまでとは違って先生の高校時代など、
今の先生を構成するルーツのお話が聞けてとても楽しかったです。
中でも現在スタートアップに携わられている先生が、最初は基礎研究にしか興味がなかったというお話にはとっても驚きました!
現在、Dセンターにおいて新しい大学のかたちを模索されている…ということで、
今後も宇治原先生のご活躍から目が離せません。
(インタビュアー・細居さんより)
——おわりに
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
「紹介していいかも!特別号・TOIC NAGOYA先生紹介リレー」第1回はいかがでしたでしょうか。
今後も名古屋大学の先生から、研究やご自身の活動のルーツについてや先生同士のご交流について伺い、発信していきます。
次回ご紹介する先生は、
名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 心の発達支援研究実践センター 名誉教授兼招へい教員・
松本真理子先生 です。
お楽しみに!